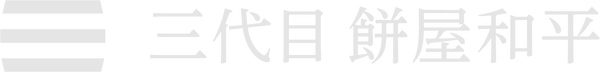餅屋和平のつきたてニュース!

お歳暮マナー完全ガイド|贈る時期から選び方、遅れた時の対処法まで
年末の挨拶として、日頃お世話になった方へ感謝の気持ちを込めて贈る「お歳暮」。 古くから続く日本の大切な贈答文化ですが、「いつからいつまでに贈るべき?」「贈るのが遅れたらどうすればいい?」など、 マナーに悩む方も多いのではないでしょうか。 この記事では、大人が知っておきたいお歳暮の基本的なマナー、地域ごとの時期の違い、 そして喜ばれる品物の選び方までを詳しくご紹介します。 お歳暮とは?その由来と意味 お歳暮は、単なる贈り物ではなく、一年を締めくくるにあたり、 日頃の感謝や「来年もよろしくお願いします」という挨拶を形にしたものです。 * 由来 元々は、年の暮れに祖霊を祭る「御霊祭り」に必要な供え物を持って、親戚やご近所を訪ねる習慣(歳暮回り)に由来しています。 この習慣が江戸時代以降、都市部で「日頃お世話になった取引先や上司へ感謝を伝える贈答習慣」として定着しました。 * 贈る相手 主に、両親や親戚、勤務先の上司、仲人、恩師、取引先など、特別な配慮や支援を受けた方々へ贈ります。 * 贈る時期 お歳暮は継続的に贈ることが基本とされており、一度贈ったら、相手や自分の状況が大きく変わらない限り、 毎年贈るのが礼儀とされています。 お歳暮を贈るのはいつからいつまで?地域による時期の違い お歳暮の時期は、地域によって慣習が異なるため注意が必要です。 特に関東と関西では、スタート時期に約10日の差があります。 地域 贈答期間の目安 関東地方 ...

風林火山!武田信玄ゆかりの地「山梨県」を巡る歴史探訪の旅
山梨県は、戦国時代最強と謳われた武将、武田信玄公が拠点とした地であり、 県内には今もなお、信玄公の偉業と歴史が色濃く残っています。 武田信玄の足跡を辿り、歴史を探ってみましょう! 武田信玄とは 武田信玄(1521年〜1573年)は、戦国時代を代表する現在の山梨県である甲斐国の戦国大名です。 本名は武田晴信で、出家後に「信玄」と名乗りました。 信玄公は、軍旗に記された「風林火山」の旗印と、徹底した情報戦、そして強固な家臣団によって、 戦国最強と謳われる武田騎馬隊を率いました。 内政面でも、領民の生活を安定させるため、治水事業や法制度の整備に尽力するなど、 優れた政治手腕を発揮した名君としても知られています。 ゆかりの地のご紹介 山梨県内には、信玄公の生涯に関わる重要な場所が数多く点在しています。 1. 武田神社(たけだじんじゃ) 場所: 甲府市 歴史: 信玄公が生まれてから亡くなるまでの約50年間を過ごした躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)の跡地に建てられた神社です。 現在は武田氏館跡として国の史跡に指定されています。 ■ 見どころ 勝負運・開運のパワースポットとして有名で、当時の堀や石垣の一部が残っており、戦国のロマンを感じさせます。 2. 恵林寺(えりんじ) 場所:甲州市塩山 歴史:信玄公の菩提寺であり、武田氏滅亡の際には、織田信長の攻撃を受け、 快川紹喜禅師が「心頭滅却すれば火もまた涼し」という名言を残した地として知られています。 ■ 見どころ...

老舗和菓子店、三代目餅屋和平が語る、和菓子と洋菓子の魅力
普段どちらも食べることが多いと思いますが、皆さんは和菓子と洋菓子の違いを意識して考えたことはありますか? 実は、和菓子と洋菓子は、主に使用される材料と栄養構成に根本的な違いがあります。 洋菓子はバターや生クリームなどの脂質が多く、和菓子は小豆や米粉などの糖質が中心。 この違いが、カロリーや健康効果に大きく影響しています。 この記事では、老舗和菓子店である三代目餅屋和平が語る、和菓子と洋菓子のそれぞれの特徴をご紹介します。 それぞれの魅力を理解し、あなたのライフスタイルに合わせたスイーツ選びを楽しんでください。 和菓子と洋菓子の違いは? 和菓子と洋菓子の大きな違いは、主に使用される主原料と油脂にあります。 和菓子は、米粉、もち米、小麦粉といった穀物や、小豆などの豆類、 そして寒天を主原料とし、バターや生クリームといった油脂をほとんど使用しないのが特徴です。 このため、食物繊維や植物性タンパク質が豊富で、低脂肪である傾向があります。 一方、洋菓子は、小麦粉、卵、砂糖に加え、バターや生クリームなどの動物性油脂を多く使用します。 そのため、脂質が多く高カロリーになりやすいですが、活動のためのエネルギー源としては非常に優秀です。 この油脂の違いが、それぞれの風味や食感の大きな差を生んでいます。 和菓子の栄養と健康効果 和菓子は、シンプルな原材料から、洋菓子にはない健康的なメリットがあります。 低脂肪でヘルシー 和菓子の主原料である小豆(餡)や米、寒天には、体にとって嬉しい栄養素が詰まっています。 例えば、小豆には食物繊維やポリフェノール、鉄分が豊富に含まれており、便通改善や抗酸化作用が期待できます。 また、寒天由来の食物繊維は、急激な血糖値の上昇を緩やかにする助けにもなります。 全体として、和菓子は洋菓子と比べて脂質の使用量が極端に少ないため、低脂肪でヘルシーです。 主に糖質でエネルギーを補給しますが、小豆や寒天の働きにより、穏やかなエネルギー補給となり、脳や体の疲労回復に役立ちます。 カロリーや健康を気にされる方にとっても、和菓子は選びやすいスイーツと言えるでしょう。 和菓子は「心の栄養」と「文化の彩り」 和菓子は、文化面でも大きな影響があります。 日本の伝統美や季節感を映し出した和菓子は、日本人の心を掴んでいます。 ...

失敗しない!新築祝いのマナー完全ガイド|相場・タイミング・喜ばれるプレゼント
新築祝いは、友人や親戚がマイホームという新たなスタートを切る際の、心からのお祝いの気持ちを伝える大切な機会です。 しかし、「いつ渡すのが正解?」「いくら包むべき?」など、マナーに悩む方も多いのではないでしょうか。 この記事では、新築祝いを贈る上で知っておきたいマナー、相場、 そして相手に心から喜ばれるプレゼントの選び方までを、完全ガイドとしてご紹介します。 新築祝いとは?引っ越し・移転祝いとの違いを解説 まず、新築祝いを贈る前に、その意味と似たお祝いとの違いを理解しておきましょう。 新築祝いの定義 新築祝いは、新しく家を建てたことに対して贈るお祝いです。 人生で大きな買い物であるマイホーム完成を祝福する意味が込められています。 引っ越し祝い・移転祝いとの違い ■ 新築祝い → 新築の一戸建てやマンションを購入したとき。 ■ 引っ越し祝い → 中古の一戸建てやマンションを購入・賃貸し、引っ越しをしたとき。 ■ 移転祝い → 会社や店舗が移転したとき(個人宅へは通常使わない)。 贈る相手が「新築」か「中古・賃貸」かで、表書きが変わることがあるため注意が必要です。 【関係性別】新築祝いの適切な相場とマナー 新築祝いの金額は、贈る側と受け取る側の関係性によって大きく変動します。 相手に気を遣わせすぎず、失礼のない相場を確認しましょう。 1....

50%が「挨拶なし」の時代に、ご近所との関係を築く「引っ越し挨拶」の新常識
引っ越しは新生活の始まりですが、その際に悩むのが「ご近所への挨拶回り」ではないでしょうか。 ある調査では、50%以上が挨拶を「していない」と回答する時代ですが、より快適で円満な新生活をスタートさせるために、 挨拶が重要になる理由と喜ばれる手土産をご紹介します。 なぜ挨拶は必要?より良い関係を築くための理由 形式的だと思われがちな挨拶ですが、新生活をより快適で安全なものにするための重要な意味を持っています。 1. 防犯・防災における協力体制の構築 日頃からの住民同士の連携は、防犯や防災の面で大きな力となります。 顔見知りの関係であれば、「見慣れない人がいたら声をかける」「災害時に助け合う」といった協力体制がスムーズに築けます。 2. 生活音や騒音によるトラブル予防 集合住宅でも一戸建てでも、生活音や子どもの声、ペットの鳴き声などによるトラブルは起こりえます。 挨拶を済ませて顔見知りになっておくことで、万が一、ご迷惑をかけてしまった場合でも、 相手に相談しやすく、円満に解決できる土台を築くことができます。 3. 地域コミュニティへのスムーズな参入 自治会やゴミ出し場の利用など、地域のルールを知る良い機会にもなります。 挨拶回りは、地域の情報を教えてもらう最初のチャンスです。 最新事情を解説!引っ越し挨拶の「する/しない」問題 ある調査では、50%以上が挨拶を「していない」と回答し、特に若い世代でその傾向が顕著に見られます。 挨拶をしない背景には、「仕事が忙しい」「知らない人と話すのが苦手」「必要性を感じない」といった理由が挙げられます。 しかし、快適な生活空間を維持するためにも、引っ越しの挨拶回りをするメリットはあります。 どこまで行くべき?挨拶の範囲と手土産の金額相場 挨拶に行く範囲は、住居形態によって調整が必要です。 挨拶の範囲(集合住宅の場合) 両隣と上下階の住人。生活音で最も影響を受ける可能性があるため、この範囲は必ず挨拶をしましょう。 管理人さんや大家さんなど、共有部分で関わる方々にも挨拶をすると、より丁寧です。 挨拶の範囲(一戸建ての場合)...

【三代目餅屋和平】和菓子の定番「小倉餡」とは?その魅力と粒あん・こし餡との違いを解説します
どら焼き、大福、最中など、日本の和菓子に欠かせないのが「あんこ」です。 あんこと一口に言っても、様々な種類がありますが、特に高級なイメージがあり、根強い人気を誇るのが「小倉餡」です。 この小倉餡とは、一体どんなあんこで、粒あんはこし餡とはどう違うのでしょうか? 小倉餡はどんなあん? 小倉餡とは、粒あんの一種で、皮まで残した大納言小豆や普通小豆の粒を活かしたあんこに、甘さ控えめのこし餡や練り餡を混ぜて作られたあんこのことを指します。 小倉餡の特徴 小倉餡の最大の魅力は、風味の豊かさと食感にあります。 ・粒の存在感 皮を破らずにふっくらと煮た小豆の粒が、しっかりとした食感を残します。この粒の存在感が、あんこ全体の味を深めます。 ・上品な甘さ 一般的に、小倉餡は他のあんこよりも砂糖の量を控えめにし、小豆本来の風味を活かすように作られます。 粒の甘さと、混ぜられた滑らかな餡の甘さが絶妙なバランスを生み出します。 小倉あんの由来 「小倉」という名前は、現在の京都府にある小倉山に由来すると言われています。 古く、小倉山付近で栽培された小豆は、特に色が美しく、風味も豊かであると評判でした。 この小豆を使って作られたあんこが、やがて「小倉餡」と呼ばれるようになったとされています。 この名前には、京都の雅な風情や、高級な小豆への敬意が込められています。 「つぶあん」と「こしあん」の違い 粒あん 小豆の皮をそのまま残し、粒の形を活かして煮たあんこ。 小豆本来の食感と風味を最も強く感じられる。 こし餡 小豆を煮た後、皮を取り除いて裏ごしし、滑らかにしたあんこ。 口当たりが非常に滑らかで、上品な甘さが特徴。 小倉餡 粒あんにこし餡や練り餡を混ぜたあんこ。 粒あんの食感と、こし餡の滑らかさの両方を兼ね備えた、贅沢な味わい。 一般的なあんことの違い 小倉餡と他のあんことの違いは、製法と価値にあります。 ①混ぜ合わせる技術...